私は資源ゴミを捨てるのがもったいなくて、牛乳パックやお菓子の空き箱を再利用するのが好きです。
机の引き出しを開けた瞬間、「あ、ここにこの空き箱がピッタリはまるんじゃないか」と思いつく。試してみると本当にピッタリ。パズルのピースがカチッとはまったような、あの気持ち良さ。
余ったピース(牛乳パックや空き箱)があると、どこかにはまらないかなって家の中を見て回ります。すぐに見つからなければ、しばらく放置してまた考える。いつか必ずはまる場所が見つかる。
不要だと思われていたものが、必要なものに変わる。マイナスがプラスになる瞬間です。
この時、ふと思ったんです。
「自分の中から勝手に湧き出るものを活かすことができれば、どれだけ効率が良いことだろうか」
では、その”自分から湧き出る資源”はどんな瞬間に現れるのか。
私は、その兆しとして小さな感情の揺れがそっと現れることが多いと感じています。
その感情に従って行動することが一番自然で、エネルギー効率が良い。感情がないと、動き出すのに必要なエネルギーがより大きくなる。
自分の感情に気づいても反応しなければ、無駄に消えていきます。利用しない感情は物理的なゴミにはならないけど、ゴミと一緒で捨てられていくだけ。
せっかく芽生えた感情を行動にしていく——これは、ゴミの再利用と似ています。
そしてブログ記事を書くことも、まさにそうでした。
ブログが続かない原因は「自分の資源」を活かせていないから
資源というと堅苦しく聞こえるかもしれませんが、ここでいう資源とは「自分の中から自然に湧き出てくるもの」のことです。
作曲家の資源はメロディで、作詞家の資源は詞です。
ブロガーにも色々な資源があります。
「日常の小さな出来事を切り取る観察力」が資源の人もいれば、「最新情報をいち早く見つけてまとめる情報収集力」が資源の人もいます。「商品を徹底的に使い込んでレビューする粘り強さ」が資源の人もいるでしょう。
では、私の資源は何か。
それは、「問題に直面した時、工夫して乗り越えようと調べ・考え・試行錯誤する探究力」です。言語化は得意ではないけど、伝えるために頑張る。このプロセスが好きなんです。
資源は「得意なこと」ではなく、「好きなこと」「気がついたら、時間を使ってること」です。
夢中になれること。エネルギーを使っている感覚がないこと。自然と向き合えるもの。
これが、自分から湧き出る資源の正体です。
その資源を誰かの役に立つように変換する。これが一番良い仕組みだと思います。
自分の資源を活用することはエネルギー効率が良く、継続するのが苦になりません。
ブログを無理なく続けるための「資源の見つけ方」
まずは自分にどんな資源があるのか、探してみましょう。
1. 自分が何に時間を費やしているか見る
資源を見つけるコツは、自分が普段何に時間を費やしているかを見ることです。
休日に何をしている? 気づいたら何時間も経っている作業は?
嫌いなことや苦手なことは、すぐにやめてしまいます。やっていて苦痛だからです。
でも、好きなことなら続けられる。これが自分の資源を見つけるヒントです。
私の場合、AIと壁打ちするのが大好きです。好きなテーマなら何時間でもできます。
一つの疑問から始まり、解決したら別の疑問が生まれ、延々と続けられる。この「一つのテーマを中心に調べたり・考えたりする」ことが、私には自然にできるんです。
これは多分ですけど、苦手な人もいるんじゃないかと思います。だから私はブログ記事を書く時はAIを最大限に活用します。それが自分に合っているからです。
2. AIに「これって普通?」と聞いてみる
自分の特性に気づくために、AIに「これって普通?」と聞いてみるのも効果的です。
AIとの対話で見えてくるのは、客観性です。
自分の癖や特徴って、意外と自分では分からないもの。でもAIに「これって普通? みんなもそうなの?」と投げかけてみると、「それ、あなたの武器になりますよ」と教えてくれます。
自分にとっては当たり前のことが、実は他の人にはできないこと——そんな発見があるんです。
他人から見たらすごい才能なのに、本人は気づいてないパターンが多い。AIは、その客観的な視点を提供してくれます。
3. 時間をかけられること自体が才能
一つのことに時間をかけられることだけでも、すごいことです。
「才能がない」と諦める人がいるけれど、世の中に天才なんて実はいません。どれだけ時間をかけたかによってレベルが変わるだけです。
そして、時間をかけられるということ自体が才能なんです。それが好きだから、自然と時間を使える。これこそが自分の資源です。
見つけた資源をブログ記事に変換する方法
自分の資源を見つけたら、次はそれをブログ記事に変換していきます。
ブログを書き始めるタイミング:入口は「興味」と「感情」
書き始めるきっかけは、興味のあることや感情が動いたことをベースにします。
「必要だから調べて考える」「これが気になる」「解決したい」——こういう感情が湧いた時が、書き始めるタイミングです。
ワンテーマずつ作る。気になるテーマが自然に生まれたら、そこから始める。
無理やりテーマを絞り出すのではなく、自分から湧き出るものを待つ。これがエネルギー効率の良い書き方です。
これは「意図的な無計画」と言えるかもしれません。計画を立てないことを、あえて計画にする。縛りを作らず、興味の湧く方へ自由に進んでいく。この自由さが、継続するエネルギーを生み出します。
記事が自然に枝分かれしていく流れ
実際に、どんな風に記事が増えていくのか。私の例をお見せします。
最初は「なぜ自分はブログ作業が続かないんだろう?」という疑問でした。
この疑問からAIと対話を始めたんです。対話の中で自分の特性に気づき、その気づきを記事にしました。
そして記事を書いている最中に、また新しい発見がありました。「自分には『核から始めて補う』という書き方が合っている」と。これもまた別の記事になりました。
さらに、以前書いた記事を見返した時、熱量の違いに気づいたんです。熱量の高い記事には共通点があり、低い記事にも共通点がある。その差は「誰かに本気で教えてあげたい」と思えるかどうかでした。この気づきも、ブログで書きたくなる内容になります。
このように、一つの疑問から始まり、書く過程で新しい疑問が生まれ、それがまた次の記事になる。これが自然に枝分かれしていく仕組みです。
ブログネタが自然に枝分かれしていく仕組み
一つの記事を書いていると、その過程で新しい疑問や気づきが生まれます。
それがまた次のテーマになる。自然に枝分かれして広がっていくんです。
今、必要な情報を追いかけていると、気づいたら自然に全体図が埋まっていた——それが理想です。
これが、クラスター記事の自然な増え方であり、「自分から湧き出る資源」を拾い続ける仕組みです。
私にとっては、クラスター記事が集まって全体を作っていく——これが一番自然なやり方です。
まとめ
牛乳パックや空き箱を再利用するように、自分から湧き出るものも活かしていく——不要だと思われていたものが、必要なものに変わる瞬間です。
自分の資源に気づくことが、充実感につながります。
ブログ記事を書く時も同じです。自分の試行錯誤、疑問、発見——それらすべてが記事になります。
同じ悩みを持つ人に届き、誰かの役に立つ。
そして何より、自分の資源を活かしているから、無理なく継続できるんです。
まずは、自分から湧き出るものを見つけることから始めてみませんか?
自分の資源を見つけたら、次はそれを記事にする番です。クラスター記事先行型戦略|深掘りタイプがピラーページで挫折する理由で、実践手順を詳しく解説しています。

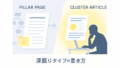
コメント